

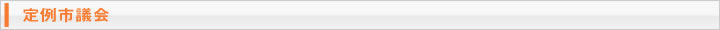
十四日、日本共産党の川口ともこ議員は、一、市民の命と健康を守る保健医療を(1)後期高齢者医療制度について、一般質問しました。
来年四月から、75歳以上の高齢者を現在の国保や組合健保などから脱退させ、後期高齢者だけを被保険者とする新しい医療制度がはじまります。年金から天引きされる保険料が将来的に上がる仕組みや、受ける医療は限定される包括払い制の方向も示され、医療の抑制や高齢者の生活を脅かす問題があります。
保険料低く抑える手立てを
厚生労働省は、年金二〇八万円の場合、平均で月六二〇〇円、年間七万四四〇〇円になると試算しています。これは、所得割など能力に応じて負担する応能負担が50%、均等割などの応益負担50%ですが国保などの県内平均の応能応益割合は7対3です。市の国保のように応能応益の割合を66%、34%と応益負担を小さくして低所得者でも納めやすいように配慮することが求められています。
川口議員は、「保険料は広域連合議会で決めるが、低所得者の保険料を低くするためにどのような方法があるのか」と質問しました。 保健医療部長は、「応益割の部分を下げること。県の補助制度などが考えられる」と答弁しました。
減免制度受けられるのか!
低所得者には、保険料を軽減する制度もありますが、それでも家族などが失業した場合減免が受けられる仕組となっているのかただしたところ、「広域連合議会で検討されていくものと考えている」と同部長の答弁でした。
広域連合に働きかける−市長
老人保健法の観点から「保険証を取り上げてはならない」とされてきましたが、滞納後一年で保険証をとりあげ、資格証明書を発行。さらに、保険給付の一時差し止めの制裁措置も設けられました。資格証の発行で病院にかかれず死亡するケースも出ています。
川口議員は、市内の後期高齢者は約二万五千人、うち所得が三十三万円以下の人が約一万五千人で全体の約六割をしめる。収入が無くても保険料を納める仕組みを考えると、資格証発行までのセイフティネットとしての減免制度は必要で、資格証も発行するべきではない。広域連合議会など何らかの形で申し入れを行っていただきたいと要求し市長に見解をただしました。
市長は、保険料などの減免や資格証明書の発行については広域連合で決めることとなっている。市としては適正に配慮してもらうように広域連合に働きかけてまいりたいと答えました。
市独自の出前講座行うべき
また、川口市議は、広域連合議会に公聴会の設置を求めていくこと、介護保険スタート時のように、市内の老人会や公民館などで高齢者とその家族を対象に出前講座を旺盛に開くよう迫りました。
保健医療部長は、自治連合会や老人クラブなどにも積極的に情報提供や説明会を行い制度の周知に努めると答弁しました。
ページトップへ