

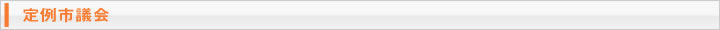
生活保護水準引下げは許されない
〜かきた有一議員が一般質問〜
|
十一日かきた有一議員は1.生活保護行政のあり方について、と題して一般質問をおこないました。
生活保護制度は平成十六年から七十歳以上に支給されていた一六六八〇円の老齢加算が段階的に廃止されました。また、母子加算については、一八才以下を一五歳以下に引き下げ、さらに今年度から一人あたり二一六四〇円の加算が段階的に減らされ廃止となります。一方で、就労する母子世帯等に「ひとり親世帯就労促進費」が支給されることになりますが、就労が困難な世帯の受給が増えている実情からもかけ離れています。
わずかな持家まで取上げるリバースモーゲージ制度
さらに、持ち家がある生活保護対象者にはその不動産を担保に生活資金を貸付けるリバースモーゲージという制度が進められています。この制度は、評価額五百万円以上の居住用不動産を持つ六五歳以上の高齢者が対象で、評価額の七割を限度に利息付きで生活資金の貸付を行います。限度額まで借りないと生活保護を受けさせないというものです。国はこの制度を、拒む場合、保護受給を停止、新規申請は却下するという内容です。
ケースワーカー不足できめ細かな対応が困難
かきた議員は、就労の見込みの少ない高齢者からわずかな持ち家を取り上げる
非情なやり方だと批判。国に意見をあげるべきだと提案しました。
また、市の生活保護体制を見てみると、ケースワーカー一人あたりの平均担当数が一一四世帯となっており、標準数の八〇世帯と比較しても大幅に多くなっていることが明らかになりました。市の生活保護体制は県内他市や他の中核市と比べても最低水準で、丁寧な対応に支障が出るのではないかと認識を問いました。
福祉部長は、家庭訪問等で対応する機会も少なくなり、きめ細かな対応が困難になる場合も生じる。事務処理も増え、過重労働も懸念されるため、適正な職員配置を確保するよう努力すると答えました。
生活の苦しさを理解し市民の立場で生保行政を
かきた議員は、国会で行われている生活保護基準引き下げの議論について触れ、生活保護基準は、介護保険料や地方税の非課税基準、国保や公営住宅家賃、公立学校授業料など各種制度の減免基準など広範囲に影響を及ぼす。生活保護は、憲法二十五条で保証される生存権を実現する国の社会保障制度のあり方の根幹にあるものだと指摘しました。また、この水準以下で暮らす人がいるのであればその人に生活保護を適用するべきで、生活保護の基準を引き下げる理由にならないと批判し、国が進める弱者切り捨ての政策に対し、自治体として、市民の立場に立った生活保護行政を進めて欲しいと要請しました。
ページトップへ