

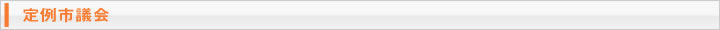
問題だらけの後期高齢者医療制度 かきた有一議員が質疑
|
低所得者に大きな負担が
保険料をみると、応益割が高くなるため、年金収入が百六十八万円以下(単身者)の場合、国民健康保険に比べても保険料が高くなり、低所得者への負担が大きいことが明らかになりました。保険料は、年金収入が年十八万円以上の人は年金から天引きされることになります。(ただし、介護保険料との合計金額が年金額の半分以上になる場合は天引きしない)
県の補助や市独自の減免は
埼玉県は全国と比較しても保険料が高くなりますが、広域連合が求めていた県独自の補助金も実現していません。低所得者が重い負担となるが、市独自の減免制度などを検討したのかとの問いに対し市は、「減免は広域連合条例で定めているため独自減免は検討しなかった」と答弁しました。
高齢者へ差別医療が懸念
受けられる医療の内容については、厚生労働省から診療報酬体系についての骨子が提出されており、その中では「係りつけ医」「包括払い」「終末期の自宅での看取り」などが示されていることも明らかになりました。七十五歳で線引きされ、それまでの医療と異なる診療報酬になるため、高齢者を受け入れると病院経営が厳しくなるなど、医療関係者からも制度に反対する声が多数上がっています。
責任はどこがとるの?
保険料が払えない人からは保険証の取り上げが懸念されていますが、市は機械的に取り上げることはせず、ていねいに対応すると答弁しました。しかし、この制度の責任はどこがとるのかとの問いに明確な答弁はなく、保険証が取り上げられない保証はありません。
柿田議員は、高齢者・低所得者に大きな負担を強い、差別的な医療制度だ、自治体も大きな負担となると指摘し、市長の考えをただしました。
舟橋市長は、「一部凍結といっても半年、一年たてば解除されて負担がやってくる。実際に市民に対応するのは市なので、保険料を払えない人などをどうするのかなど今後考えて整備していかなくてはならない」と答えました。
ページトップへ