

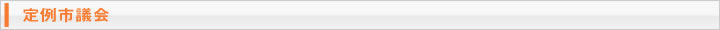
地域農業を応援して食糧自給率の向上を かきた有一議員
|
三月十三日、かきた有一議員は「食糧自給率と市の農業施策について」一般質問をおこないました。
食品偽装や穀物の高騰など食品不安のニュースが日々取上げられています。一方、農業の現場を見ると日本の食糧自給率は三十九%、埼玉県も川越市も自給率十一%という深刻な状況にあります。
川越市は、県内でも有数の農産地であり、学校給食に地元の農産物を取入れたり、直売所を通して地産地消の取り組みも広がりつつありますが、思うように自給率は伸びていません。
川越市の農業の実態は
かきた議員は、川越市の農業従事者、耕地面積の推移などの現状がどうなっているかただしました。
農家戸数、農業従事者とも減少しており、農地も平成七年と比較して九五二ヘクタール(二六・四%)も減少しています。農家の内訳を見ると、六五歳以上の従事者が三六%、兼業農家と自給的農家で八五%を占めている状況が明らかになりました。
農産物直売所が好評
新鮮で安全・安心な地場農産物を直接販売する農産物直売所が平成十七年に芳野地区に、平成十九年に福原地区に開設されています。 消費者からは、品揃えの豊富さや、新鮮な野菜が評価され、利用者も増加しています。
一方、直売所に出荷する生産者を見ると、いままで販売をしていなかった農家も参加するなど、取り組みが広がっています。
やりたい人を支える農政を
政府は食糧輸入自由化路線の下、大量輸入を進める一方で、生産者には減反を押し付け、さらには価格政策を廃止し、一部の大規模経営にのみ助成金を出すというやり方をはじめています。しかし、川越市の農業の実態を見ても、高齢者や小規模の農家が多数を占めており、こうした人たちが地元農業を支えています。
かきた議員は、直売所などをさらに広げ、小規模の農家も参加できる地元の農業を応援することが必要だと指摘し、今後の農政ついてただしました。
細田副市長は「平成二十年度は目標を策定する。地産地消の徹底、ブランドづくりによって消費拡大を図る。遊休農地の活用とともに、市内農地を最大限有効活用し収穫回数を増やす。団塊世代のリタイヤが見込まれるなかで新規就農者を対象にした研修を実施するなど担い手の確保に取り組んでいく」と答えました。また、農産物の安全性については「農薬や化学肥料の使用を減らす有機農法や減農薬農法に取り組むとともに、天敵などの自然の仕組みを利用した効果的な防除技術などを普及させていく」と答えました。
ページトップへ